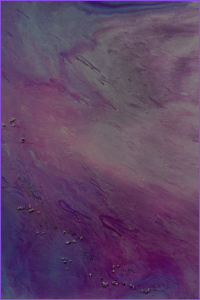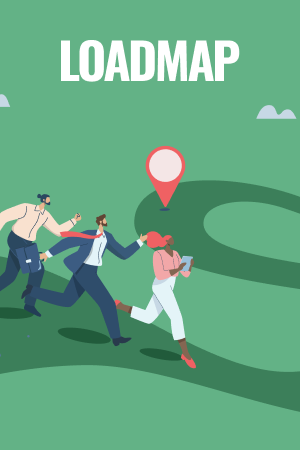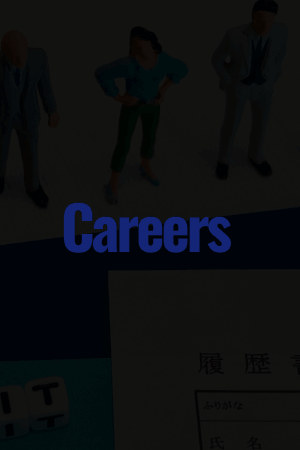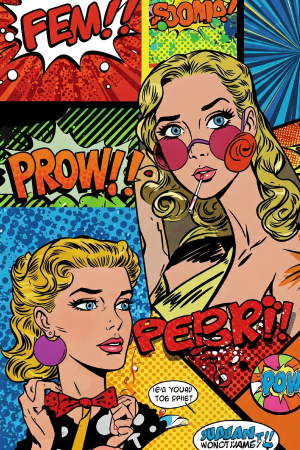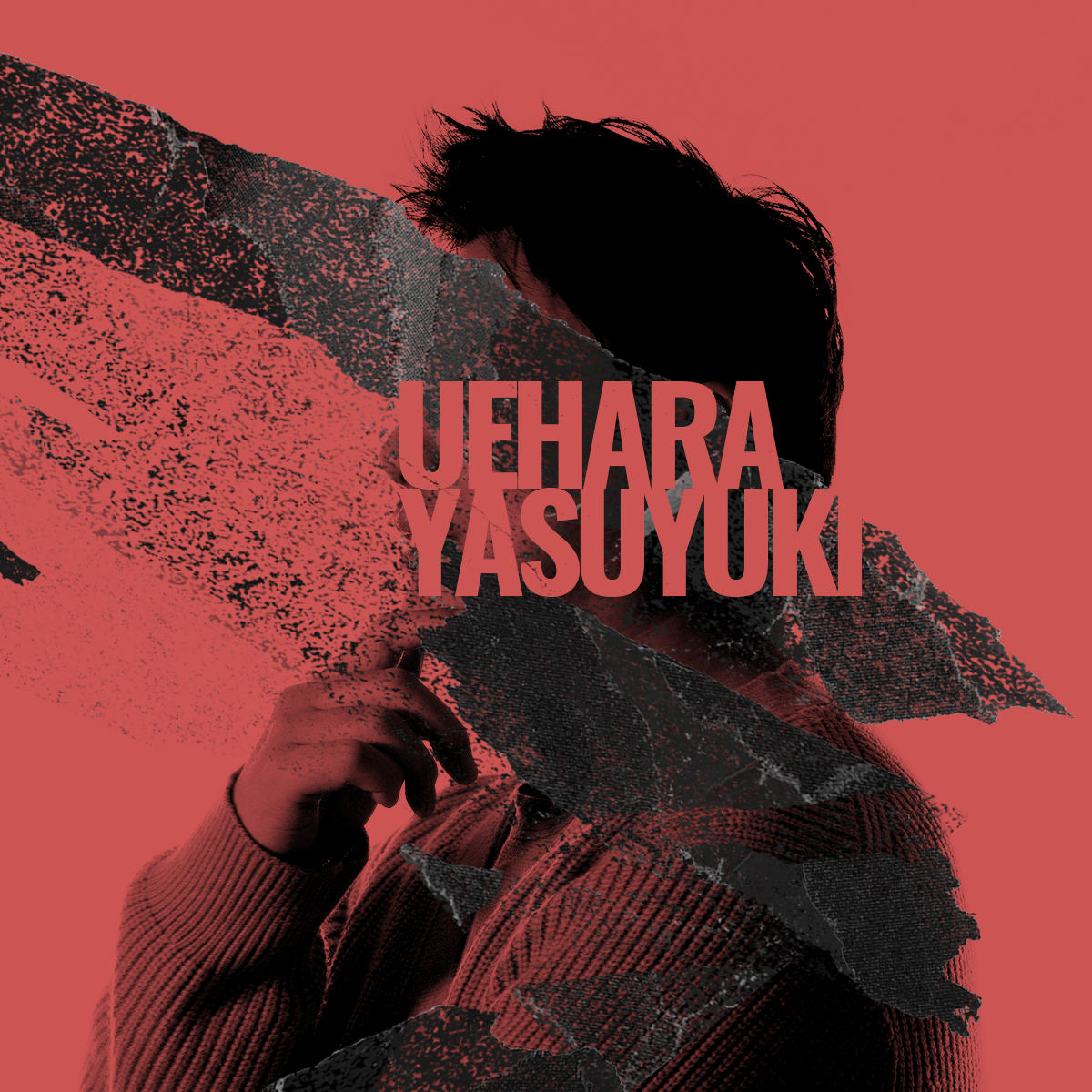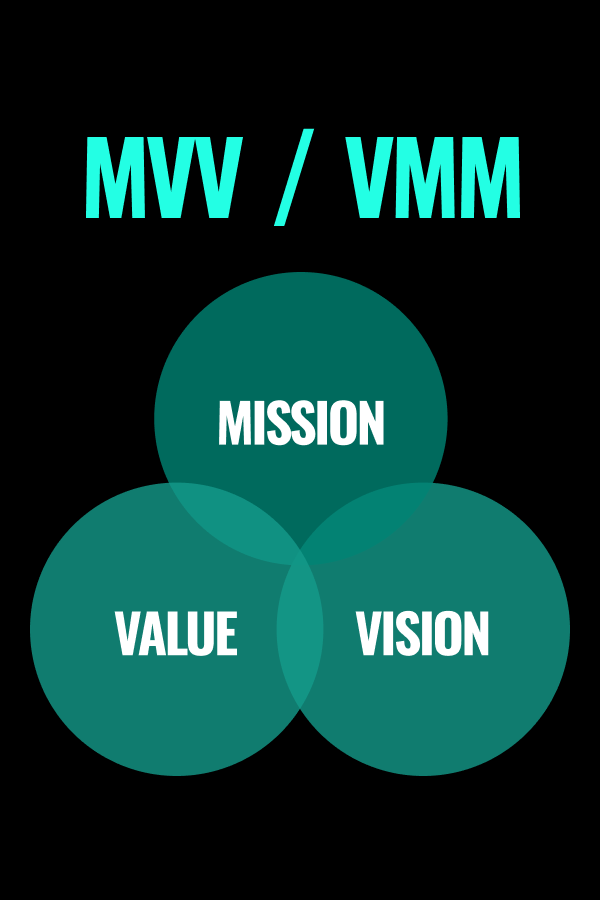INDEX
0.はじめに
私は音楽が好きで、特にMr.Childrenやレミオロメンといったアーティストをよく聴きます。その中である日を境に聴く頻度が明らかに減りました。
減った原因として大きかったのは、小林武史さんがMr.Childrenやレミオロメンのプロデュースから離れたことだと思います。
プロデューサーは、なかなか目立たないポジションではありますが、音楽に限らず制作には大きく影響します。その中で音楽理論やコード進行的なものは分かりませんが、私なりに小林武史さんの凄さを3つ紹介できればと思います。
1.まず小林武史さんとはどんな人なのか
小林武史さんは、Mr.Children、レミオロメン、My Little Lover、サザンオールスターズ、MISIA、椎名林檎、Bank Bandなどを手がけた日本の音楽プロデューサー・作曲家です。J-POPの発展に大きく貢献し、映画音楽の制作、Mr.Chilrenの櫻井和寿、音楽家・坂本龍一と一般社団法人「ap bank」を立ち上げ社会活動にも取り組むなど多方面でご活躍されてます。
2.緩急を使った楽曲
Mr.Childrenやレミオロメンなどプロデュースした曲の中で、緩急を使った曲が多いです。
Mr.Childrenの場合は、代表曲のHANABIもその1つです。
1番と2番のサビの前の間奏のメロディーで、音数を減らして“溜めてからサビに向かう”構成がとても特徴的です。
レミオロメンの場合は、2006年のアルバム『HORIZON』に収録されているスタンドバイミーです。
この曲も3番の大サビ前に音数を減らし、盛り上がりを引き立てる構成が特徴的です。HANABIと同様の手法が使われています。
小林武史さんの楽曲では音数を減らして、一番盛り上がるサビ引き立たせる楽曲が多く、これは日本のJ-POPシーンで広く支持される要因のひとつであると言っても過言ではないと思います。
3.キーボードやシンセサイザーの取り入れ方が心地のいい構成になっている
小林武史さんの楽曲では、キーボードやシンセサイザーも特徴的です。その中で個人的に好きな2曲をご紹介します。
こちらがMr.ChildrenのWorlds endという曲のイントロ部分ですが、バイオリンとドラムの音に沿うようにしてキーボードの音が聴こえるかと思います。他の楽器の音に自然に寄り添うようにキーボードの音が重なる点が、個人的に非常に心地よく感じられます。
こちらはanderlust(読み方: アンダーラスト)という男女2人組のユニットのバンドのヒカリという曲です。この曲のイントロの効果音のような音がシンセサイザーです。こちらも個人的に、ドラム音から始まりそこから並行するようにシンセサイザーの音が始まりますが、このように並行して流れるシンセサイザーの音が、個人的にとても好きです。
4.大胆かつ壮大な構成
小林武史さんの編曲の中で、バイオリンを使う事が多く、またそれが壮大さを生み出します。その中で個人的に好きな2曲をご紹介します。
Mr.Childrenのしるしは、バイオリンを使用し、3番サビで転調することで、壮大さを演出しています。そのため耳にインパクトが残ります。オーケストラ仕込みも小林武史さんの特徴的でもあります。
アイランドはレミオロメンというと、前向きなメッセージ性の高い曲が多いイメージですが、この曲はその真逆です。ダークな雰囲気の楽曲でも、オーケストラ的なアレンジと2度の転調によって、絶望から希望まで這い上がる曲構成がすごく好きで、毎日聴いています....
5.まとめ
制作に携わる立場として、ディレクターやプロデューサーによって作品の表現が大きく変わることを、身近な好きなアーティストを通して改めて実感しました。
小林武史さんは、曲構成やキーボードの音色が特徴的なので、聴いてすぐに「あ、小林武史さんっぽい」と分かる楽曲もあります(すべてではありませんが笑)。
なので、私も作り手として、特徴ある個性や表現を生み出せる存在を目指したいと思っています。


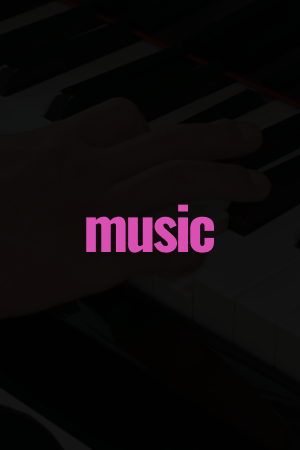


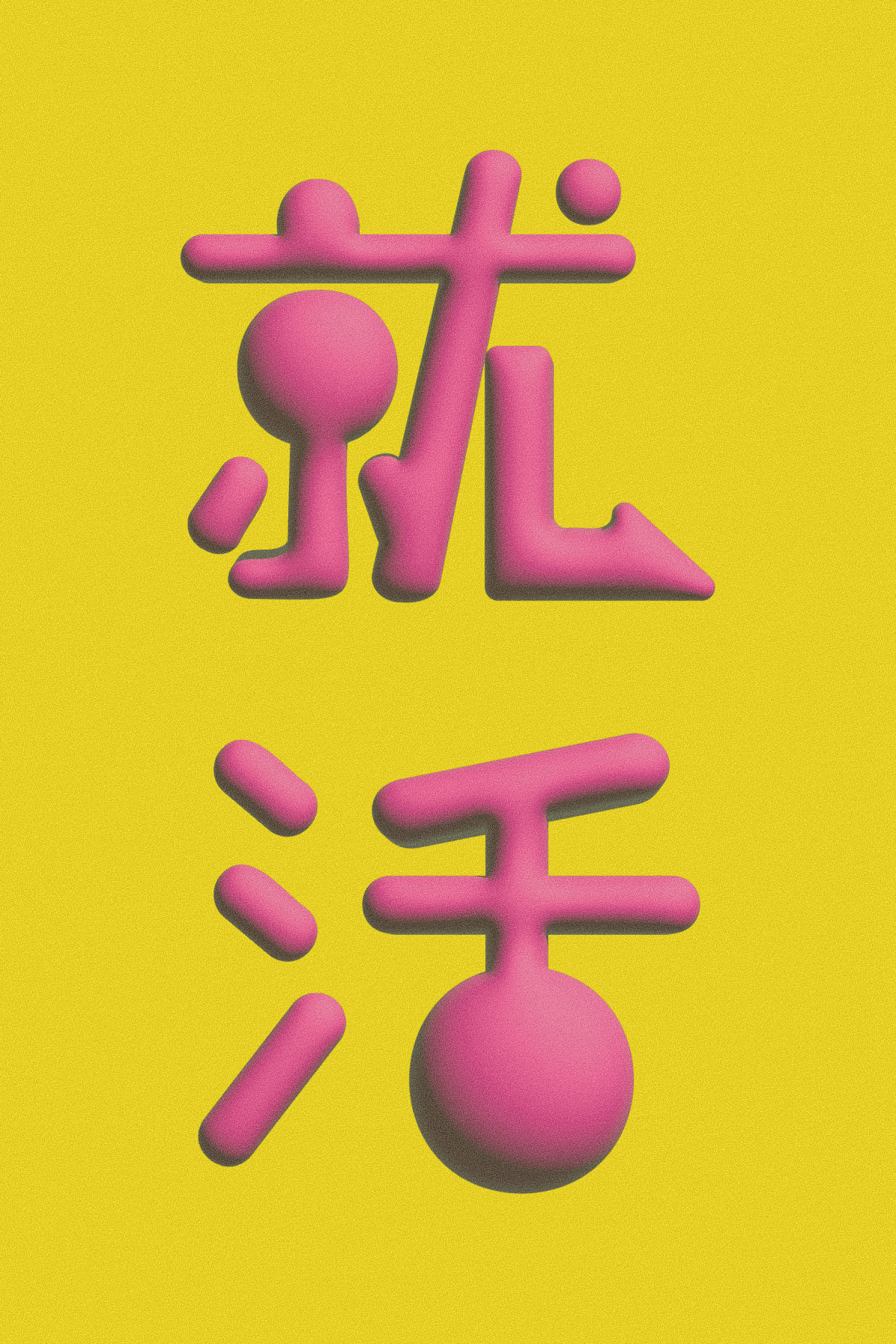
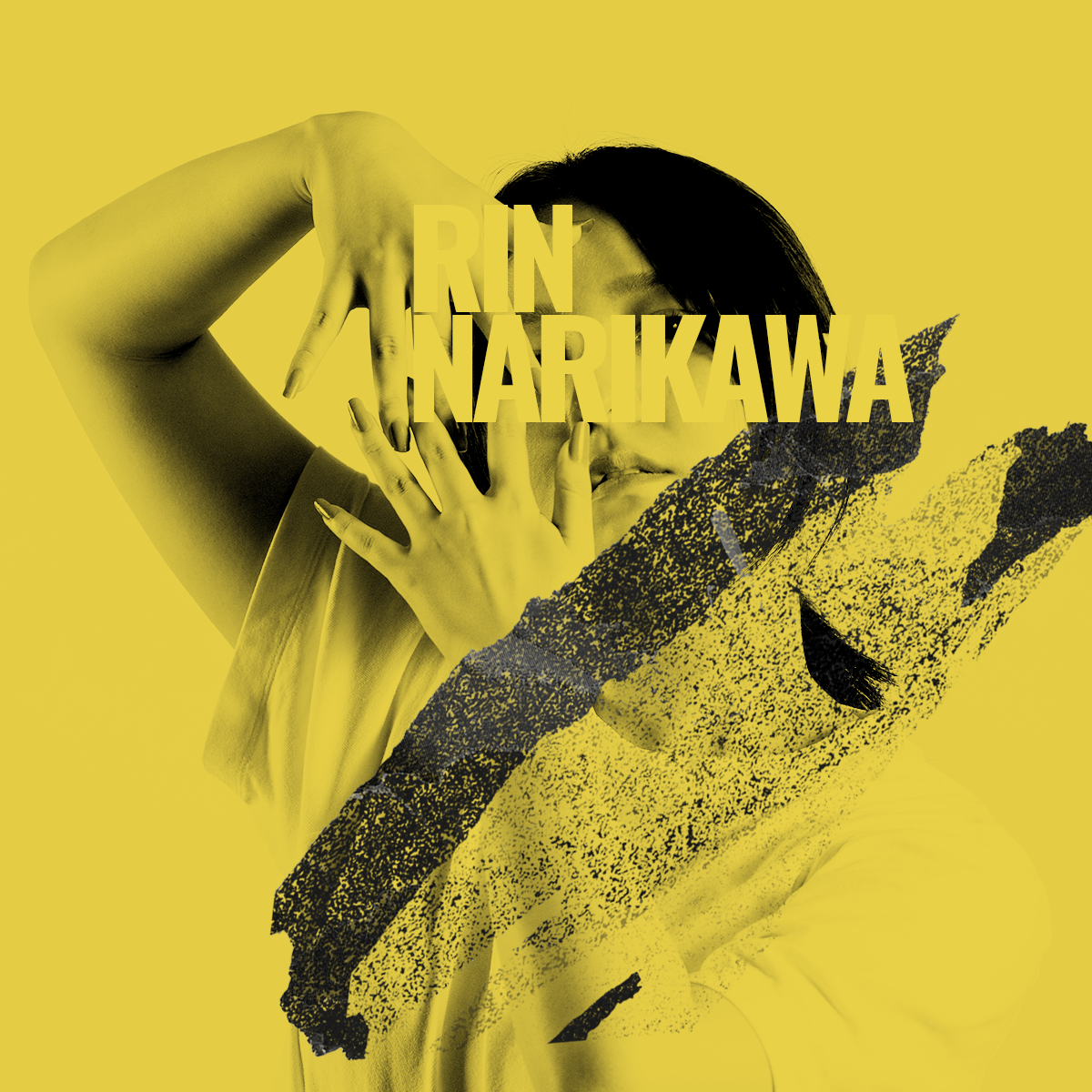
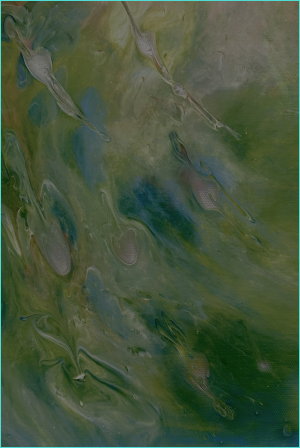
.png)